この記事の信憑性

今回は、吹き抜けについて解説します。
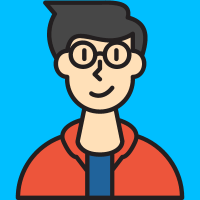
吹き抜けのあるマイホームにしたい!
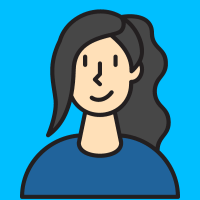
吹き抜けのデメリットを知りたい!
このような方は是非ご覧ください。
マイホームの間取りに「吹き抜けを採用したい!」と考えている方は多いです。

私も吹き抜けを採用しました!
お洒落で開放的なマイホームになるので、とても人気の間取りですが、吹き抜けがある住宅のデメリットを把握していない方は意外と多いです。
そこで今回は、実際に吹き抜けの住宅に住んでいる私が、吹き抜けのデメリットを解説します。
皆さんが1番に想像するデメリットは「家の中が寒くなること」だと思いますが、それ以外にもデメリットはたくさんあります。

後悔の原因になるので必ず把握してから契約しましょう!
目次
一条工務店で吹き抜けを採用する時のルール
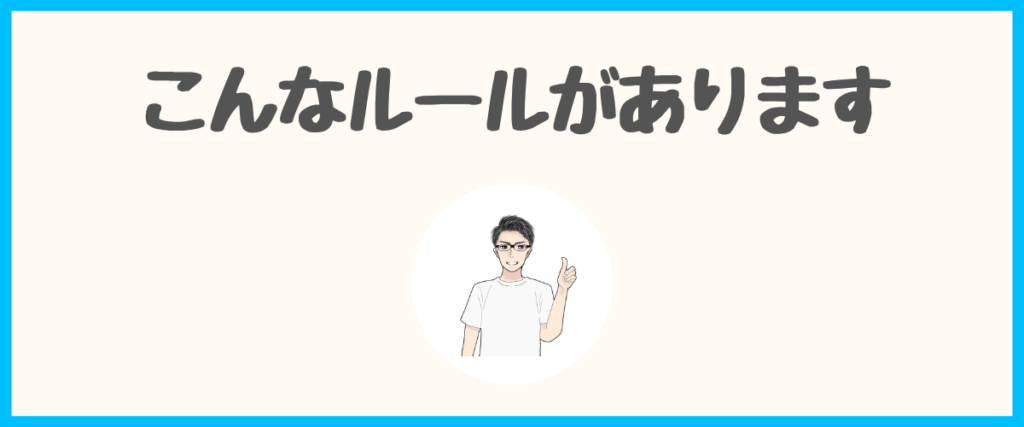
まず初めに、一条工務店の吹き抜けルールについて紹介します。
一条工務店の吹き抜けにルールがある理由は、住宅性能を担保するためです。

基本的に、吹き抜けのある住宅は耐震性能が低くなってしまいます。
夢だった吹き抜けのあるマイホームになっても、耐震性のない家になってしまうと元も子もないと思います。
ですので、ある程度の耐震性を担保する為に吹き抜けにはルールがあります。
それでは、一条工務店で吹き抜けを採用する場合のルールを紹介します。
吹き抜けのルールについて詳しく解説していきます。
吹き抜けの広さは『床面積の1/3』まで
1つ目のルールは、吹き抜けの広さは『床面積の1/3 』までにしなければならないことです。
例えば床面積が30坪の家で吹き抜けを採用する場合、吹き抜けの面積は「30坪の1/3 である10坪」までと決められています。
吹き抜けの幅は『住宅全体の幅の1/2』まで
2つ目のルールは、吹き抜けの幅は『住宅全体の幅の1/2』までにしなければならないことです。
例えば住宅全体の幅が20mだとすると「吹き抜けの幅は10mまで」と決めれています。

以上の2つが、一条工務店で吹き抜けを採用する時のルールでした。
他にも、一条工務店で吹き抜けを採用する際に覚えておいてほしいことは、吹き抜け部分の坪単価です。
一条工務店は、吹き抜け部分の坪単価が1/2の価格になります。
例えば、1坪 80万円のシリーズにした場合、吹き抜け部分の坪単価は『1坪 40万円』という計算です。
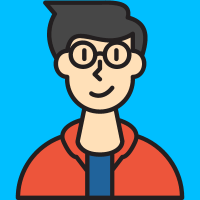
1階を広いリビングにしたいけど、住宅価格は抑えたい!
このような方は、吹き抜けを広めにすることで、少しでも住宅価格を抑えることができます。

因みに、階段部分は通常価格になります。
予備知識として、バルコニーも坪単価が半分になります。
バルコニーには、床暖房や壁がないので坪単価が半分になるとのことでした。
以上が、一条工務店の坪単価ルールになります。
吹き抜けのデメリット7選
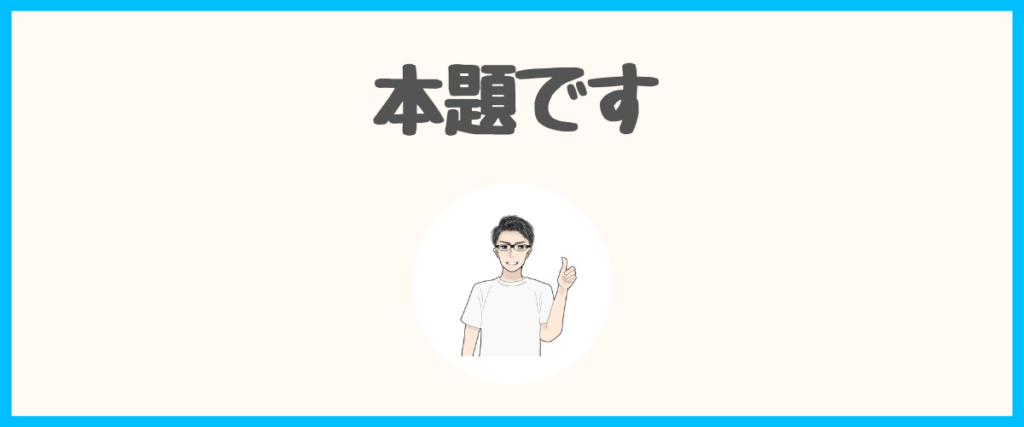
それでは、吹き抜けのデメリットについて解説します。
吹き抜けのデメリット7選は以下の通りです。
詳しく解説します。
ニオイが2階に漏れる
吹き抜けのデメリット1つ目は、ニオイが2階に漏れることです。
吹き抜けにすると、物理的に壁や扉がないので1階のニオイが2階に漏れます。
このような、キツイ匂いは2階まで漏れてしまいます。
一晩経つとナノイーが活躍してくれてニオイはだいぶ落ち着きますが、物理的に壁や扉がないので、匂いが2階に漏れやすくなることはデメリットだと思います。
1階の生活音が2階に音漏れする
吹き抜けのデメリット2つ目は、1階の生活音が2階に音漏れすることです。
物理的に音を吸収する障害物がないので、1階の音は2階まで音漏れします。
会話の内容までは聞こえませんが、会話をしていることは気づくレベルです。
このような生活音が、2階にまで音漏れしてしまうことは覚えておきましょう。
1階と2階の境目に白い板
吹き抜けのデメリット3つ目、1階と2階の境目に白い板が入ることです。
吹き抜けを採用すると、1階と2階の境目にこのような白い板がつきます。
全体図

拡大図
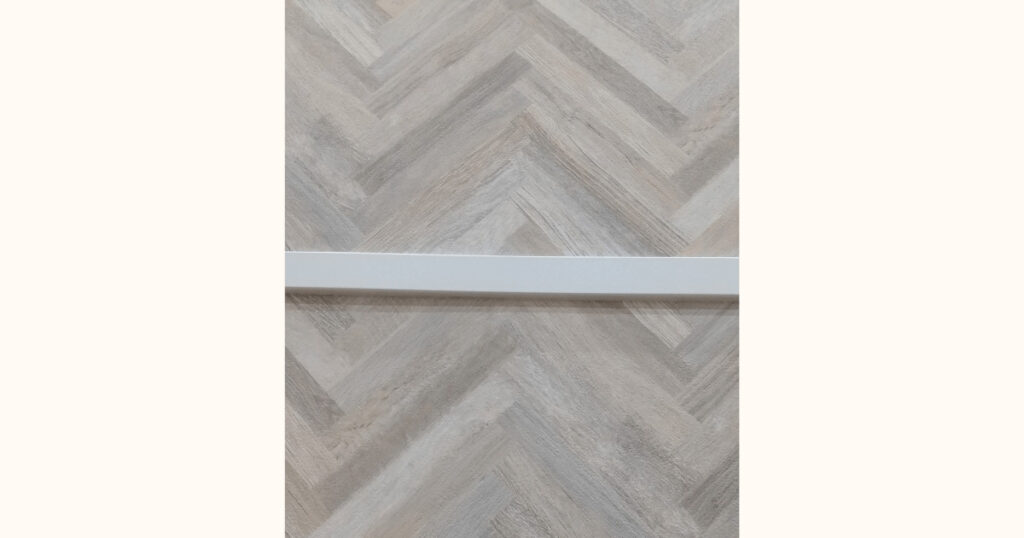
このような白い板がつくと、クロスの雰囲気が少し変わってしまいます。
また、吹き抜け部分のクロスをオプションに変更すると、2面分のオプション料金が発生します。
白い板があることで、「白い板より上側で1面分、白い板より下側で2面分」このようにカウントされてしまうので、オプション料金が2倍になります。

今でも納得していません。笑
自動のハニカムシェードが増える
吹き抜けのデメリット4つ目は、自動のハニカムシェードが増えることです。
吹き抜け部分の窓には、物理的に手が届かないのでハニカムシェードの自動開閉オプションを追加しなければなりません。

1箇所1万円前後のオプション価格です。
もし、ハニカムシェードをつけないと、日中の太陽の光が直接家の中に入ります。
その結果、直射日光によってクロスは色褪せしてしまいます。
2階が狭くなる
吹き抜けのデメリット5つ目は、2階が狭くなることです。
一条工務店には『原則、2階建てを総二階』にしなければならない。というルールがあります。

総二階とは、1階の坪数と2階の坪数を同じにすることです。
原則、2階建てを総二階にしなければならないので、自動的に2階の坪数は減ってしまいます。
耐震性が落ちる
吹き抜けのデメリット6つ目は、耐震性が落ちることです。
冒頭でも軽く触れましたが、吹き抜け住宅は耐震性が落ちます。

流石の一条工務店でも耐震性は落ちます。
窓の掃除が大変
吹き抜けのデメリット7つ目は、窓の掃除が大変になることです。
吹き抜けの窓は手が届かない位置にあるので掃除が大変になります。
窓拭きはもちろん、窓台にもホコリは溜まるので、脚立や長い棒を利用して掃除する必要があります。

大掃除の時しか気が向きません。笑
【まとめ】一条工務店の吹き抜け

【吹き抜けのデメリット7選】実際はどうなの? 一条工務店のルールも紹介でした。
本日の内容を振り返ります。
吹き抜けのデメリットは以下の7つです。
- ニオイが2階に漏れる
- 1階の生活音が2階に音漏れする
- 1階と2階の境目に白い板
- 自動のハニカムシェードが増える
- 2階が狭くなる
- 耐震性が落ちる
- 窓の掃除が大変
基本的に、吹き抜けにすると耐震性は落ちてしまうので、一条工務店で吹き抜けを採用する場合、以下のルールが決められています。
- 吹き抜けの広さは『床面積の1/3』まで
- 吹き抜けの幅は『住宅全体の幅の1/2』まで
私も採用していますが、吹き抜けがあると「開放感」があり「お洒落な家」になります。
とてもオススメする間取りなので、デメリットも頭に入れた上で吹き抜けを採用するようにしましょう。
以上、参考になれば嬉しいです!
ではまた!
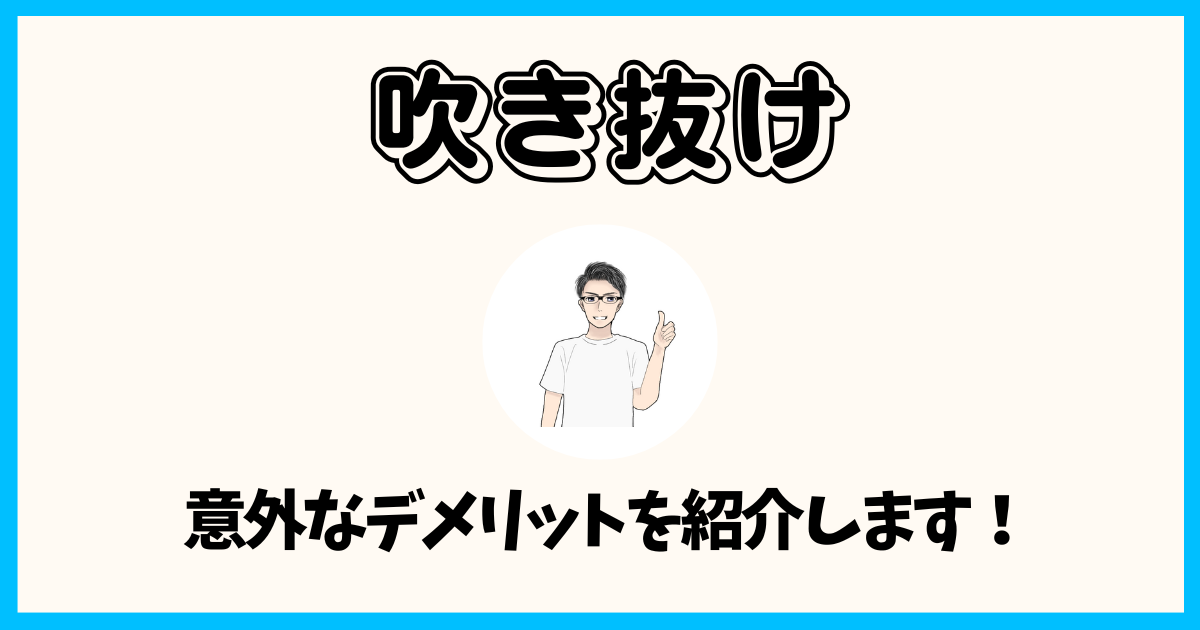

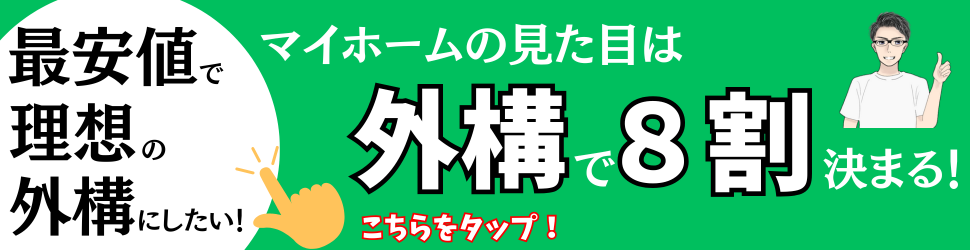


コメント